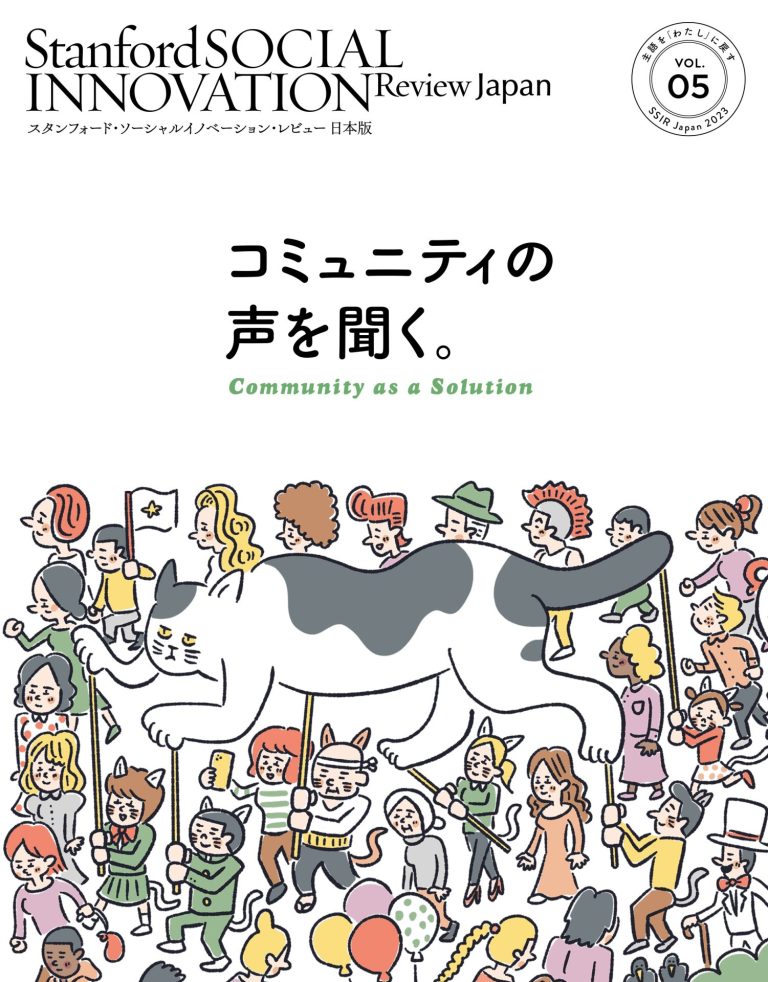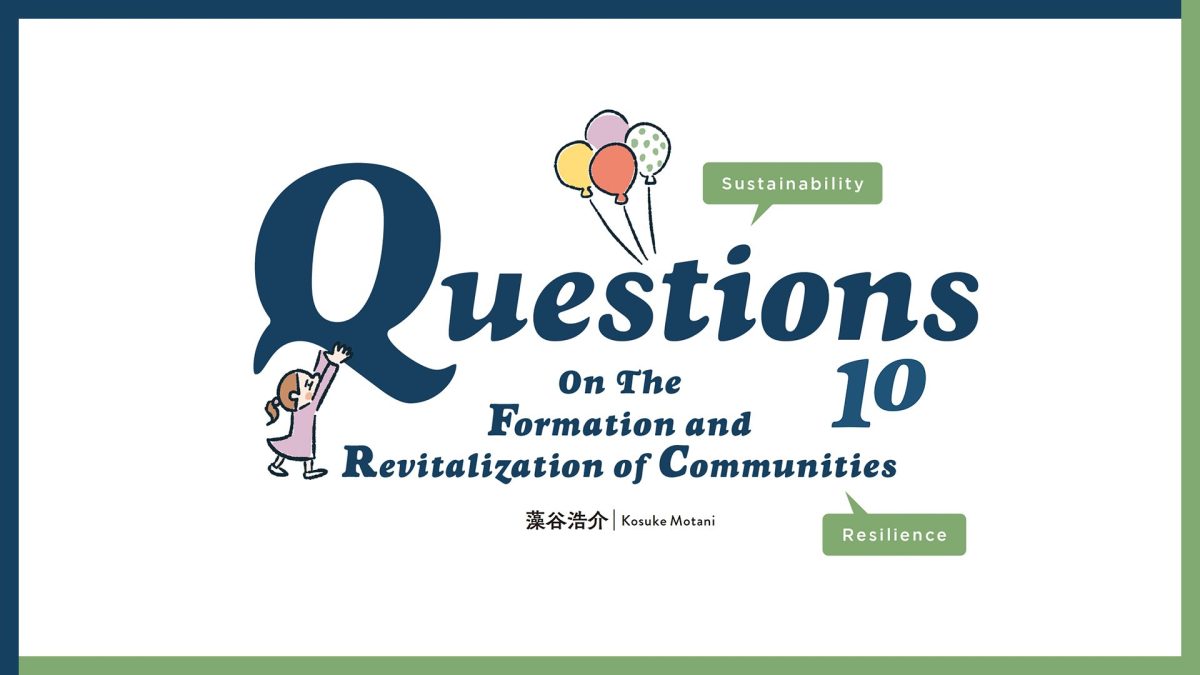
なぜ里山の循環再生システムに人は引き寄せられるのか
生活のなかで「かけがえのない私」を実現
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』のシリーズ「コミュニティの創造と再生をめぐる『問い』」より転載したものです。
藻谷浩介|Kosuke Motani
お金を否定せず、依存せず
「里山資本主義」という概念を、NHK広島放送局の取材班が打ち出したのは11 年前のことだ1。当時私は、彼らが中国地方の各地で制作したシリーズ番組に、ナビゲータとして出演し、貨幣経済を代替・補完するものとしての里山の経済循環の仕組みを紹介した。
里山とは生態学の用語だ。農山漁村の周辺にあり、薪や山菜などを採りに人々が日常的に足を踏み入れている樹林帯を意味する。そこでは人と自然が長年にわたり共生しながら、生き物の循環と再生が継続して行われてきた(その反対概念が「奥山」)。その生態学用語を冠した里山資本主義は、最初は文字通り「里山で営まれる資本主義」だったのだが、循環再生という要素を再現できれば、農山漁村に限らず都会でも実践可能である。
そもそも資本主義の本来の意味は「資本に投資し、循環再生させて利子を得る」ことではないか。そして、資本のなかでもヒト・モノ・情報といった分野は、お金が発明される以前から存在した。ヒトという資本は、循環再生されれば次世代という利子を生む。森林という資本からは薪炭という利子が得られる。田畑を開墾すれば作物という利子が採れる。街道や建物などの資本は、通常は償却されて価値が消えていくものだが、「景観」や「デザイン」を備えたものには経年価値(ビンテージ)という利子がつく。
そういう認識に立って再定義すれば、里山資本主義とは人的資本(ヒト)、自然資本(自然物)、物的資本(人工物)、知的資本(情報)の4つを循環再生させながら、人間の生存に必要な水・食料・エネルギーを利子として受け取る仕組みだといえる。もちろんその過程では、金銭を稼いで何かと等価交換する営みも普通に行われる。金銭は分業を可能にする手段であり、これを介した価値の交換なくしては、里山資本主義とて成り立たない。しかし金銭の利子(運用益)には期待しない。また、お金を介した等価交換だけでなく、自給、物々交換、恩送り(見返りを期待せず、他人にあげてしまうこと)といった、お金を用いない生産・交換手段も重視する。
生活保護費のデータから見えてくるもの
生活のなかにお金に依存しない部分が増えることで最も救われるのは金銭収入の減る老後である。貯金のなくなった高齢者が最後に頼るのが生活保護だ。現に、生活保護受給世帯の50%以上が高齢者世帯である。保護率で見ても、65歳人口で約3%と総人口の倍近くになっている2。
高齢化の進んだ地方ほど生活保護に頼る人が多くなる、と普通は思うだろう。それがそうでもないのだ。2014年時点の地域別人口1人あたりの生活保護費というデータがある3。人口1人あたりの生活保護費が日本で最も多いのが東京都台東区で、12万8600円だ。2位が大阪市の11万8000円と続く。
では、2023年5月に震度6強の地震に見舞われた石川県の珠洲市と、東京都千代田区ではどちらの数字が高いだろうか。珠洲といえば能登半島の奥地の不便な過疎地であり、人口は約1万3000人、高齢化率も高い。一方の千代田区は1人あたりの市町村民税収額が港区に次いで全国で2位と富裕層が多い。答え合わせをすると、千代田区が2万5000 円であるのに対し、珠洲市は9100円。お金に困っている高齢者が珠洲市では千代田区よりはずっと少ないというわけだ。
もう少し数字を見てみよう。東京23区の平均をとると5万6200円。財政破綻した北海道の夕張市の4万8000円よりも高い。東京都港区は2万7000円で、新潟市の2万3000円より高い。新潟の貧しさを訴えた田中角栄の時代とは隔世の感がある。生活保護費のもらいやすさは都道府県によって異なるし、県庁所在都市には受給者世帯が集まりやすいなどの傾向もあるが、それでも、過疎や高齢化率と貧困がリンクしていないことが、これらの数字から見てとれるだろう。
そもそも高齢化率を高齢化の指標の第一と考えること自体がおかしい。医療や介護の費用もマンパワーも、65歳以上人口を総人口で割った高齢化率ではなく、高齢者の絶対数の増減に連動するものだからだ。高齢者の定義も65歳以上ではなく70歳以上としたほうが、各人の健康や就労の実態に即している。そこで70歳人口の増減を確認すると、高度成長期に団塊世代が流れ込んだ大都市圏における、増加ペースが加速している。2017年から22年の最近5年間の住民票の数(外国人含む)でいうと、首都圏1都3県や愛知県は19%増、京阪神3府県は18% 増、バブル期前後から急成長したためにまだ高齢者が少なかった福岡市や札幌市は24%増となっている。自給や恩送りの習慣がない都市部では、このペースに応じて医療や福祉の供給を増やさなければならない。
一方、過疎地域の農村や漁村では既に70歳人口が減り始めている。高度成長期に若者が出て行ったままで、「年寄りのなり手」が減っているのだ。そのような自治体では、医療福祉の需要は下がり始め、その分を子育て費用に回すことも可能だ。実際、最近5年間で70歳以上人口が減った全国140弱の過疎自治体のうち、60弱で0~4歳の乳幼児が増加している。他方で首都圏1都3県の乳幼児の数は11%減、愛知県は12%減、京阪神3府県は20%の減少だ。
つまり過疎地域は、取り残されたのではなく、高齢化する日本の未来を先取りしただけなので、大都市圏に先んじて再生に向かう自治体も出てきているわけだ。
分業ではなく一人多役「過疎地は消滅に向かう」「農山漁村には経済ポテンシャルがない」といった発想は、人口規模の大きさが経済活力を決めるという先入観からくるものだろう。人口が少ないほど多種多様な人材や企業を地域内に抱えられず、リカードが重要性を指摘した「分業」、とりわけ多種多様な現代的な専門性を備えた人材による分業が成り立ちにくいという現実が、過疎地のポテンシャルを小さく見せているのではないか。
たしかに人口の少ない地域ほど、一社多役、一人多役にならざるをえない。だが現場で観察していると、むやみに分業せずに1人が多くの役割を併せ持ったほうが、かえって成果が大きくなりコストの下がる事例が多いことに気づく。サッカーでもバレーボールでも、ポジションにこだわらずに動き回ることで、穴が埋まって強く戦える。
市場に関しても、規模の大きさがかえって経済を制約することがある。全国にチェーン化してシェアを固めるほど、商品の多様性を失ううえ、日本経済の停滞に連動して業績が悪化しがちだ。大手ビール会社はその典型例だろう。反対に里山企業は、大規模化を志向せず、他地域の同業者とノウハウを教え合う。あるいは大規模化しそうな場合はのれん分けし、兄弟会社として互いに連携する。
典型的なのはワイナリーだ。テロワール(ブドウ畑を取り巻く自然環境要因)を重視し、自分たちが責任を持って送り出すワインの質に徹底的にこだわる。だからワイン生産地では、大規模ワイナリーが興るよりも、ミニワイナリーが群立する。最近15年間の相手国別経常収支を確認すると、BtoBのハイテク製品に強い日本はアメリカ、イギリス、ドイツ、また中国、韓国、台湾に対して大幅な黒字を計上し続けているが、イタリアやフランス、スペインに対しては概ね赤字である。それらの国のワイナリー、あるいはチーズや生ハムなどのローカルビジネスが、いかに強い国際競争力を持っているのかを、この事実はまざまざと示す。
一社多役のもう1つのレバレッジは、小さな垂直統合の生み出すシナジーだ。京都府南丹市にある美山里山舎という宮大工(神社仏閣などの伝統建築の新築・修理請負)の会社では、山主から林地の利用を委託され、そこへの林道敷設、木の伐採、製材、施工などをすべて自社で行っている。最終商品に必要な部材を、必要なサイズで、必要な量だけ切り出すので、無駄なコストがかからない。自社のエネルギーは副産物である木屑の燃焼や小水力発電で賄う。関連して、薪や薪ストーブ、小規模水力発電装置などの販売も手掛け、廃材、間伐材を利用したマウンテンバイクコースの創設まで行っている。敷地を借りた地元の小規模事業主が行う、飲食や宿泊、健康事業も人気だ。
このように連携と統合の仕組みによって、零細規模でも、外部資本に頼らずに価値を生み出し続けることができる。里山の循環再生システムは、無限のポテンシャルを有しているのだ。
非代替性への欲求
『里山資本主義』を上梓してから10年。新型コロナウイルス感染症の拡大を境に、「規模の拡大よりも循環再生」という論旨に賛同する人が急激に増えたように感じている。背景には、儲けや規模、人気など定量的な指標の拡大を競う「優越欲求」から、替わりのない(かけがえのない)存在になることを目指す「非代替性」への欲求へと、多くの人の志向がシフトしているということがあるかもしれない。
いま、どれだけ他に優越したとしても、いずれは次世代に抜き去られ、忘れられていく。優越欲求で生きる人生とは、歴史観のない人生ともいえる。
一方で非代替性への欲求は、歴史観と不可分だ。自分の存在のかけがえのなさは、究極的には「自分のやったことが後世に発展的に継承される」ことで証明されるからだ。より身近な言葉で言えば、「生きた爪痕を残す」ことである。誰かが開墾して残した農地、誰かが植えた山林、誰かが受け継いできたコミュニティ、これらを自分が受け継いで後世に遺せれば、それこそが自分の生きた爪痕なのだ。
循環と再生を繰り返しながら次世代につないでいくことが生活のなかに組み込まれている里山コミュニティにおいては、非代替性への欲求は叶えられやすい。分業ではなく一人多役、規模の追求ではなく学び合いやつながりによって、未来に継承される価値を生む里山資本主義の力強さを敏感に感じ取っている人たちが、若い世代を中心に確実に増えている。過疎地の高齢化問題は都会より先に深刻化し、日本の高齢化問題は諸外国より先に深刻化したが、いまや高齢者の急増はアメリカやアジア諸国のほうがはるかに急ペースだ。そんな社会をどう再構築していくか、その解決の鍵をにぎるのが、里山資本主義なのではないか。
【構成】荻野進介
藻谷浩介
地域エコノミスト/日本総合研究所主席研究員
1964年山口県生まれ。平成大合併前の約3200の市町村すべて、海外119カ国を私費で訪問。地域振興や人口問題に関して研究・執筆・講演を行っている。著書に『デフレの正体』、『里山資本主義』(NHK広島取材班との共著、角川書店)、『完本 しなやかな日本列島のつくりかた』(新潮社)、『観光立国の正体』(山田桂一郎氏との共著、新潮社)、『世界まちかど地政学』(毎日新聞出版)、『日本の進む道』(養老孟司氏との対談)などがある。
1 『里山資本主義』藻谷浩介、NHK取材班 角川書店、2013年。
2 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000908527.pdf
3 area-info.jpn.org/SehoPer.Pop.html