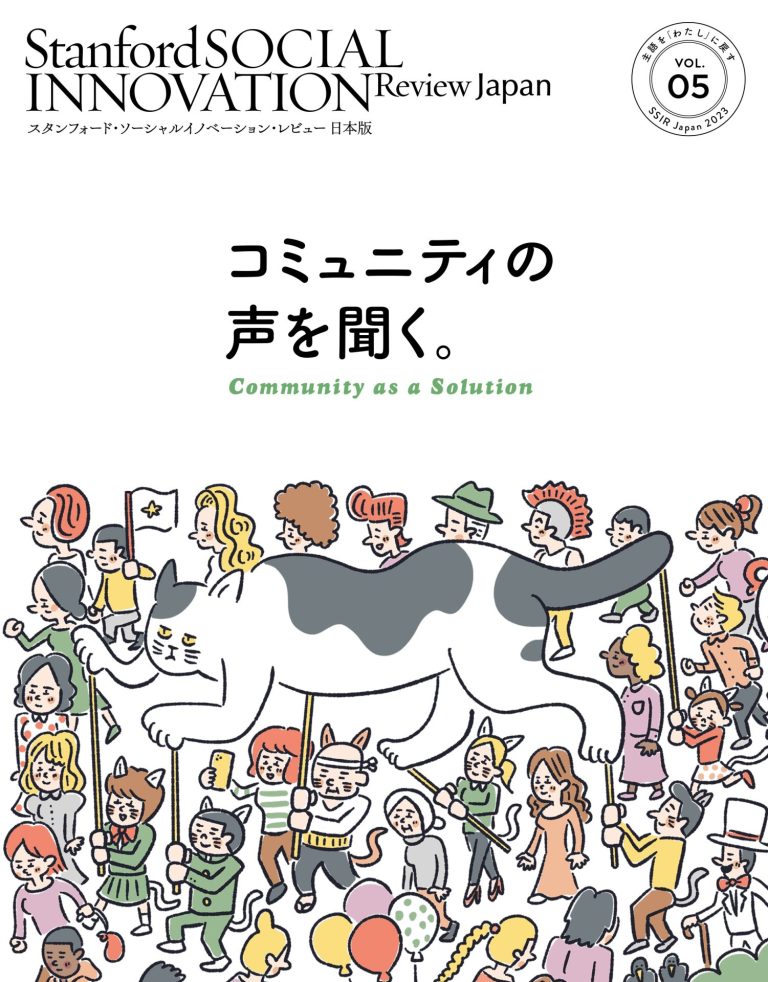70~80点の短期的な成果を長期的なシステム変化につなぐには
利害が一致しなくてもともに前進する方法
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』のシリーズ「社会を変えるコラボレーションをめぐる『問い』」より転載したものです。
小田理一郎 Riichiro Oda
複雑な問題に対して完璧でなくても70~80点の答えをどう探るか
いま、私たちにとって最も緊急の課題は気候危機だ。後戻りできないところまで行くのを食い止められるかどうかは、この10年が勝負であり、「30年や50年経てば、科学技術が問題を解決してくれる」という長期の希望的観測に頼るわけにはいかない。実は現在の技術レベルでも、短期的に十分意味ある成果を出せるのだ。完璧な解決策を待つよりも、より早期に成果を出すことこそがレバレッジの効いた施策になる。必要なのは、いますぐに、再エネ、産業・輸送・民生での省エネ・電化やライフスタイルの見直しなどのアクションを起こすことだ。
気候危機でもSDGsでも、よい活動を行っている個人や組織はいるものの、個別にバラバラの対応をしていると、この勝負の10年に必要な変化を生み出すことはできない。
だからこそコレクティブ・インパクトのようなアプローチが必要であり、私はそれを「システムそのものの構造を、そのシステムの多様な構成員が十分に集まることによる変革」と考えている。多様なプレーヤーがセクターを越えて協働し、各組織や地域、国の歴史や文化の延長線上で複雑に絡み合う構造に向き合うべきだ。
常に100点を目指すのではなく、短期的に70~80点の成果を出して次にバトンを渡すためのアクションをどう生み出せばよいだろうか。
ハードとソフトで対話をリードする
私は長年、組織改革、業務改革などの現場を経験し、現在は、システム横断で社会課題を解決するプロセスデザインやファシリテーションを手がけている。そこで活用しているのが、デニス・メドウズやピーター・センゲが発展させたシステム思考や、長年紛争解決に携わったアダム・カヘンによる対話ファシリテーションのアプローチである。
その経験から言うと、さまざまなステークホルダーが集まってシステムの変容を起こそうとするとき、最初に必要なのはお互いの関係性の変容だ。それぞれが「私の言う通りにやってくれさえすれば、うまくいく」という姿勢で話をしているうちは、コラボレーションの成果は得られない。
そこで重要なのがファシリテーターの役割で、ソフトとハードの2つのアプローチが要求される。ソフトなアプローチには「自分や他者の心の声に耳を傾けるプロセス」があり、ハードなアプローチには「具体的に何をどうやっていくのか」のアクションを見出していくプロセスが含まれる。
公共セクターでもビジネスセクターにおいても、スタート地点では「こういう施策にすべきだ」といったハードな面の議論が支配的になりやすい。
また、システムの中心にいる人たちの声が大きく、弱者の側の声が出ないという構造がよく見られる。
そのため、最初はシステムの中心にいる人たちの声やハードに関する意見を抑え、より公正なプロセスになるように、より弱い立場にある人たちの本当のニーズをすくい上げる必要がある。
ファシリテーターの支援の下、参加者が自分自身を内省しながら対話をすることで、一人ひとりの参加者の視点では見えなかった世界が見え始め、自分たちのやっていることが互いに絡み合っているということが少しずつわかってくる。それをシステム図にして整理したり、社会課題の現場や参考になりそうな事例を探したりしながら、さらに対話を重ねていく。
その後に、「じゃあ、どうするのか」という段階に移っていく。このときに「皆さんの意見は承りましたが、方針として優先順位を検討した結果、こうせざるを得ません」と結論を押しつけてしまうと、せっかくソフト面でよい関係性を築けても、振り子が元に戻ってしまいシステムは変わらない。
このような「優先順位づけ」はビジネスによく見られるが、意見が割れたときに不満を残しやすいアプローチだ。そこで私は「順序立て」と呼ぶ方法で複数のアイデアを扱っていくことを提案したい。短期的には、限られたリソースをある一点に集中せざるを得ないが、長期的に考えれば、短期的施策で得られた成果を活かした施策を採用することで、インパクトを波及させていくプラン、つまり「セオリー・オブ・チェンジ(変化の理論)」が描ける。そうすると、「最初にここをやったら、次は私たちの番だ」というかたちで、妥協ではなく納得したうえで進められる。
それでも合意に至らない場合に、最後は行政やビジネスのトップが意思決定をするかもしれない。そこで必要なのは「オープンさ」と「奉仕の心」であるとアダム・カヘンは語っている。
つまり、「自分たちの組織の都合だけではなく、ステークホルダーの意見を聞き、相互依存やジレンマを理解したうえで、自分たちはこう決めたい」ということを、透明性をもって説明できることが重要だ。
それは100点満点の解ではないかもしれない。しかし、システムの全体像を認識し、残る課題に対する学習・適応のプロセスを考慮した意思決定がなされれば前進といえる。
このような対話をリードするとき、1人のファシリテーターだけで進めるのはなかなか難しい。なぜなら、それぞれ得意分野があるからだ。複数人でファシリテーターチームをつくって、お互いの長所を活かしながらハード面とソフト面を両立できるようにしていくとよいだろう。
利害が一致しない相手と同じテーブルにつくことの意味
また、多様な利害関係者を集めるときには、つい自分と意見が合う人や利害が一致する人を誘いやすいが、利害が一致しない相手同士こそ同じテーブルにつかなければ、システム変容を起こすことはできない。
その1つの事例がサステナブル・フード・ラボ(SFL)である。『これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。』(SSIR Japan)の「システムリーダーシップの夜明け」の章でも取り上げられているが、増加する世界の人口を賄うだけの持続的な食糧システムをつくっていくことを目指し、セクター横断で食にまつわるさまざまな問題にチャレンジしている。ファシリテーターがシステム思考やU理論を駆使して、立場の異なる参加者間の対話を支援している。
SFLにはユニリーバやネスレのような業界上位を占める企業も参加している。独占禁止法に触れるリスクがあるため、彼らが直接的に協力し合うことはない。しかし、同じ場で世界の食糧や農業の問題などを議論し、それぞれが異なるパートナーや解決方法を見つけている。プラットフォームを通じてそれぞれが新しい知見や考え方を柔軟に取り入れ、切磋琢磨する関係になったのだ。
これはアダム・カヘンのいう「ラディカルなコラボレーション」、つまり根本を見据えて常識を覆すやり方での協働だと言えるだろう。
他にも、コカ・コーラとWWFが水資源保護のために10年間のパートナーシップ協定を結んだという事例がある。実は当初、それぞれ組織の内外から、パートナーシップへの反対の声が出されたという。
彼らは最初のミーティングでも、お互いの基本的な目的が異なることを認識した。しかし、合宿などの取り組みを通じて関係を構築していった結果、利害関係が合致しなくても協力できることを見出し、それが互いにプラスになると結論づけたのだ。共通の目的ばかりにこだわって利害の一致を条件にしていたら、このようなコラボレーションは生まれなかっただろう。
ラディカルなコレボレーションでは、利害が異なるプレーヤー同士がいかに共有ビジョンやアジェンダをつくれるのかが鍵になる。そのうえで施策を実行するときには、どのようにリソースを配分するのかも重要だ。レバレッジが効くポイントを見定め、集めたリソースをそこに投下し、生み出されたインパクトがそれぞれの目的に資するようなかたちで波及していく、というようなデザインが必要となる。
つまりコレクティブ・インパクトは、1つの目的を達成したら終わりではない。意図せぬ結果が生まれたときに対処し、システム全体のステークホルダーによりよいインパクトが波及していくようなデザインが重要なのだ。そのためには、コラボレーションというものに対する私たちの信念や前提、つまりメンタル・モデルを問い直していく必要があるだろう。
【構成】やつづかえり
小田理一郎
有限会社チェンジ・エージェント 代表取締役
オレゴン大学経営学修士(MBA)修了。米国企業で10年間にわたって組織横断での業務改革・組織変革に取り組む。2005年にチェンジ・エージェントを設立、経営者・リーダー研修や組織開発などのコンサルティングに従事。デニス・メドウズ、ピーター・センゲら第一人者たちの薫陶を受け、学習する組織、システム思考、ダイアログなどの普及推進を図っている。著書に『「学習する組織」入門』、訳書・解説書にアダム・カヘン著『共に変容するファシリテーション』、ピーター・M・センゲ著『学習する組織』、デイヴィッド・ピーター・ストロー著『社会変革のためのシステム思考実践ガイド』(以上、英治出版)など。