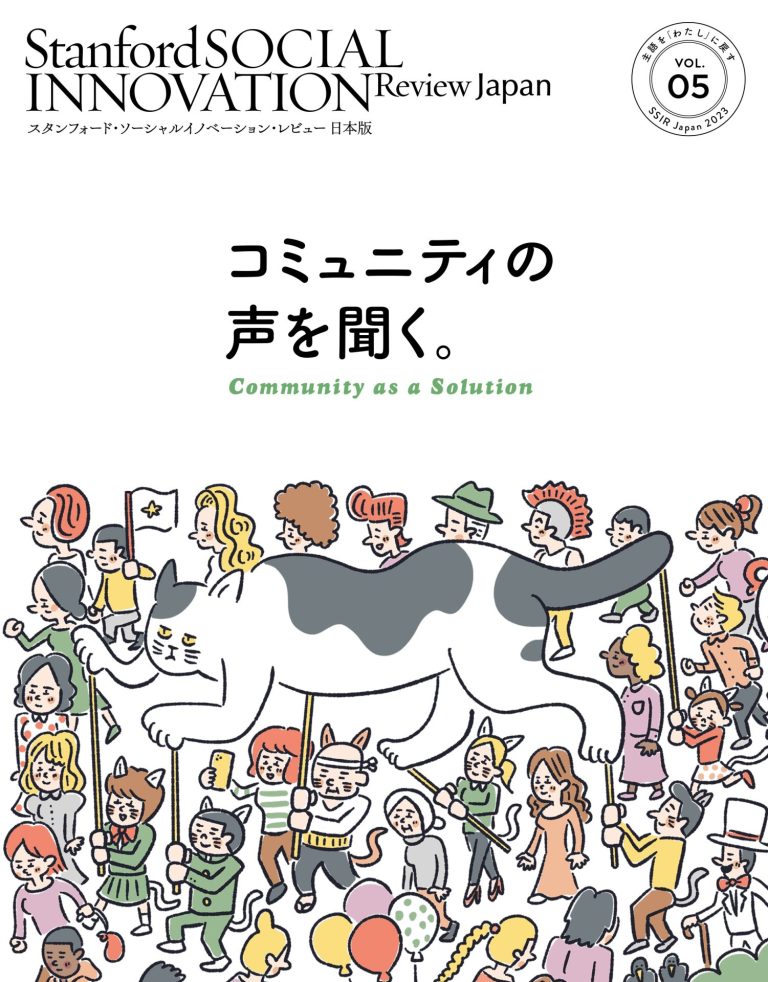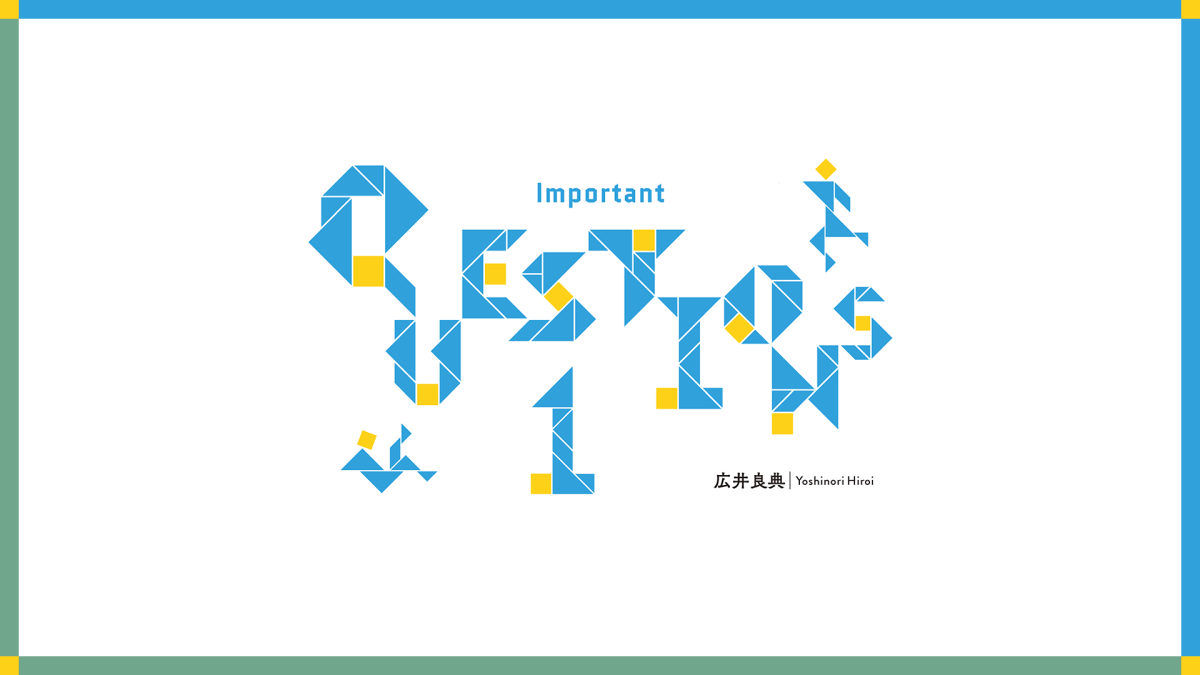
サイエンスとケアが融合したら何が起きるのか
ポスト資本主義における科学技術のあり方
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
広井良典 Yoshinori Hiroi
両輪の関係で展開してきた、近代科学と資本主義
近代科学と経済、特に資本主義は、車の両輪のような関係で展開してきた。17世紀にヨーロッパで科学革命が起こり、これが現在の近代科学の起源を成しているが、この時期は資本主義の本格的な始動期でもあった。その象徴的な出来事に東インド会社の成立がある。その後、社会の産業化や工業化が急速に発展していくなかで、科学と技術は強固に結びつき、発展を後押ししていった。こうして両輪のように進化してきた近代科学と資本主義だが、いま資源や環境レベルでの「外的限界」、そして世界がモノと情報にあふれるなかで人々の需要の飽和という「内的限界」に直面して、さまざまな課題が噴出している。
私は、科学技術のあり方を見直すということは、大きく言えば資本主義のあり方を見直すことでもあると考えている。資本主義とは「市場経済+限りない拡大・成長」を志向するシステムのことである。
歴史を俯瞰すれば、人類は人口や経済規模の「拡大・成長」時代と「定常化」のサイクルを繰り返してきた。第一のサイクルは現生人類が地球上に登場して以降の狩猟採集段階と定常化(成熟期)、第二のサイクルは約1万年前に農耕が始まってからの拡大・成長期と定常化、そして、第三のサイクルは産業革命以降の拡大・成長期である。そして、私たちは第三の定常化(成熟期)への移行期にいる。
こうした移行期には非常に創造的で、大きな意識変化が起きる。狩猟採集段階の移行期には「心のビッグバン」と呼ばれる現象があり、装飾品や絵画など文化的、芸術的な作品が一気に生まれている。また、農耕文明の移行期は、ドイツの哲学者、カール・ヤスパースが「枢軸時代」、科学史家の伊東俊太郎が「精神革命」と呼んだ時代にあたり、ギリシャ哲学、仏教、儒教や老荘思想、ユダヤ思想といった普遍的な思想や宗教が地球上で同時多発的に生まれている。
社会全体の潮目は変わりつつある
2001年に私が『定常型社会』(岩波新書)という本を出し、GDPの拡大ばかりを目指す「拡大・成長」の社会はもう終わり、人口減少や環境問題を見据えた持続可能な社会を描く必要性があると述べたとき、賛同してくれる人はいたが全体から見れば少数派だった。しかし、ここ数年の間に社会全体の潮目が確実に変わってきていることを感じている。
京都大学は日立製作所グループとともに「日立京大ラボ」を設立して、社会イノベーションに関する研究を進めているが、日立が「2024中期経営計画」のなかで重要な概念として「プラネタリーバウンダリー」を掲げているのも象徴的である。これは、スウェーデン出身の環境学者のヨハン・ロックストロームが、人間が地球上で持続的に生存していくために超えてはならない「地球の限界」を、生物多様性などさまざまな領域で定量的に明らかにして、知られるようになった言葉である。
今や企業が持続可能性を考慮することは(なかには表面的な取り組みがあるとしても)、当たり前になっているが、こうした動きには大きく分けて、「Green Growth(グリーン成長)」と「Degrowth(脱成長)」という2つの局面がある。「グリーン成長」というのは環境に配慮しながらも経済成長はこれからも続けていくもので、企業にとっては受け入れやすい。一方の「脱成長」はグリーン成長よりもラディカルな主張だ。しかし、「脱成長」への人々の関心も次第に高まっている。サステナビリティやウェルビーイングといったGDPに代わる新たな指標や価値観への転換が社会全体に広がりつつあり、そのなかで科学技術のあり方についても見直しが進み始めているのではないか、というのが希望も込めての私の見方である。
科学技術は「情報」から「生命」の段階へ
科学技術の基本コンセプトは「物質」→「エネルギー」→「情報」と移り変わっており、経済活動もそれと密接にリンクして、両者はほぼ同時進行で変化してきた。たとえば17世紀の資本主義の勃興期には、市場経済を通じた取引が活発にあり、さまざまな「物質」の流通や国際貿易が拡大した。科学革命により、物体の運動に関するニュートン力学が成立した時代でもある。やがて産業革命が起こると同時期に、電磁気や熱力学など力学では説明できない現象が注目されるようになり、19世紀には「エネルギー」という言葉がつくられ広がっていった。そして電力や石油の大量生産・消費を核にした工業化社会を導いていく。
20世紀半ばになると、「情報」というコンセプトが躍り出る。クロード・シャノンがビットの概念を体系化してデジタルの思想が生まれ、その技術的応用としてコンピュータ、さらにその社会的普及としてインターネット、SNSなどが普及していった。80年代以降、金融のグローバル化を通じた資本主義の展開が地球規模で進んでいったのも、インターネットを含む情報関連技術の発展と一体だった。そして、長いサイクルで見れば「情報」も、もはや成熟(飽和)段階に入ろうとしている。
人々は「情報の消費」から、その先の「時間の消費」に向かっており、充足的な時間を過ごすことが欲求の対象となりつつある。そのなかにはコミュニティや自然とのつながりへの志向も含まれており、市場経済を超える領域が展開しようとしている。では、科学技術の基本コンセプトにおける「情報」の次の段階は何か。私は「生命(Life)」であると捉えている。
「生命」というのは、狭義での生命科学にとどまらず、人生や生活、あるいは生態系やエコシステム、生物多様性や持続可能性といったマクロな意味も含む。生活の豊かさや幸福は、「時間の消費」とも重なるものだ。
ポスト情報化・ポスト資本主義の時代には、この「生命」がさまざまな領域で基本コンセプトとなっていくのではないだろうか。経済的にも生命関連産業として、1)健康・医療、2)環境・自然エネルギー、3)生活・福祉、4)農業、5)文化 といった分野の重要性が高まるだろう。では、「生命」の時代に、社会と科学技術との関わりはどのように変わってくるのか。
「ケア」と「科学」の融合が、近代科学のあり方を変えていく
たとえば「ケア」という領域がある。この言葉には、介護だけでなく教育や福祉、心理などの幅広い意味が含まれる。これまで「科学」と「ケア」は対照的なものだった。そもそも近代科学というのは、「人間」と「自然」を切断し、人間が自然を支配するという考え方を背景にしている。一方、ケアの領域では、当然ながら対象(相手)は単に支配される存在ではなく、自発性を持った存在という視点が必要であり、対象との相互作用を無視できない。つまり、近代科学とケアでは、対象との関わり方が非常に異なっている。
また、近代科学は要素還元主義であり、すべてを要素に分解して物事を合理的に理解しようとする。それに対してケアでは、ホリスティック医療という言葉があるように、全体の関係性を見ていくことが求められる。さらに言うと、近代科学が普遍的・一般的な法則を明らかにしようとするのに対して、ケアの領域では人間は一人ひとりが異なっていて多様であるように、対象や出来事の個別性・一回性を大切にする。「再現可能性」は科学では非常に重要とされるが、一人ひとり異なる人間が対象になるケアの領域ではそれだけでは説明できないことのほうが多い。
このように対照的だった「科学」と「ケア」は、「生命」の時代には融合していき、結果として、近代科学の性格が根本から見直されるようなことが起きるだろう。環境問題にしても、その理解や解決にあたっては個別の事象だけでなく、地球全体のシステムや関係性を俯瞰して見ることが欠かせない。またハードサイエンスの分野でも、エピジェネティクスの研究が注目されている。これまではDNAを解析すれば人間のすべての特徴がわかると考えられてきたが、実際には環境要因と遺伝子の相互作用のなかで人間のいろいろな資質が形成されていくことも明らかになってきた。対象との相互性を考えることで、これからの科学のあり方全体が大きく変容していくだろう。
私自身は「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」1 というプロジェクトをささやかながら進めている。「鎮守の森」には日本人のアニミズム的な自然観が反映されているが、それは人間が自然を支配するのではなく、自然の内発的な力をいただきながら共存していくという考え方である。これは地域コミュニティで小規模分散型の自然エネルギーを広めていく発想と非常に親和性が高い。自然エネルギーや生物多様性といった現代的な課題を、日本の伝統文化や自然観と結びつけて捉えていくことも有効ではないかと思っている。
地球環境や人間の「有限性」をどう受け止めていくか
私たちはいま第三の「定常化」への移行期にあると話したが、では、第四の「拡大・成長期」はあるのだろうか。それを可能にする要素には、おそらく3つあるだろうと考える。それは、究極のエネルギー革命である「人工光合成」技術の開発と、「宇宙開発ないし地球脱出」、そして、「ポスト・ヒューマン」である。ポスト・ヒューマンとは、人間そのものを科学技術によって改変して、資源的・環境的な有限性を乗り越えようという志向を含むもので、未来学者レイ・カーツワイルが唱える「シンギュラリティ(技術的特異点)」をはじめ、アメリカでは人間の進化の次なる段階について、さまざまな文脈で広く議論されている。
2020年にハーバード大学の遺伝学者デビッド・A・シンクレア氏が、人間は健康寿命を無限に延ばすことができるという『ライフスパン⸺老いなき世界』(東洋経済新報社)という本を出してベストセラーになったが、無限の「拡大・成長」を求め続ける志向は、特にビジネスや経済の世界ではまだ強い力を持っている。寿命を無限に延ばす、脳の情報をアップロードして機械のなかで永久に生きるといったことが真面目に論じられているが、こうした方向を追求して本当に人間は幸せになれるのかという疑問はぬぐえない。
私はむしろ「無限性」ではなく、地球環境や人間の「有限性」をどう受け止めるのかが、これからの科学技術において大きなテーマとして浮上してきていると思う。有限性を踏まえたうえで、「定常型」社会における新たな豊かさや創造性について、持続可能性とともに考えていく発想や議論こそが必要である。そもそも科学技術は社会が設定した目的や価値観に向かって発展していくものであり、いわば手段に過ぎない。その価値観の転換期を私たちは迎えている。
イギリスの建築家、セドリック・プライスはこんな言葉を残している。
Technology is the answer.But what was the question?
「テクノロジーこそ答えだ。ところで、どんな問いだったかな?」
この言葉は「何のために科学技術はあるのか?」という問いを私たちに突きつける。そして、それを決めるのは私たち人間であり、社会である。
【構成】中村未絵
広井 良典
京都大学 人と社会の未来研究院 教授
東京大学教養学部(科学史・科学哲学専攻)卒業、同大学院修士課程修了後、厚生省勤務を経て、1996年より千葉大学法経学部助教授、2003年より同教授。この間、マサチューセッツ工科大学(MIT)客員研究員として、STS(科学技術社会論)などをテーマに研究を行う。2016年4月より京都大学教授。専攻は公共政策および科学哲学。社会保障や環境、医療、都市・地域に関する政策研究から、時間、ケア、死生観などをめぐる哲学的考察まで幅広い活動を行う。著書に『定常型社会』(岩波新書)ほか、多数。
1 東日本大震災を経て、ローカルな地域に根ざした「分散型のエネルギーシステム」をつくっていくことが大きな課題であることを踏まえ、自然と一体となった地域コミュニティの拠点であった「鎮守の森」と自然エネルギー拠点整備とを結びつけ、ローカル・コミュニティの活性化を図っていくプロジェクト。鎮守の森コミュニティ研究所ホームページ参照