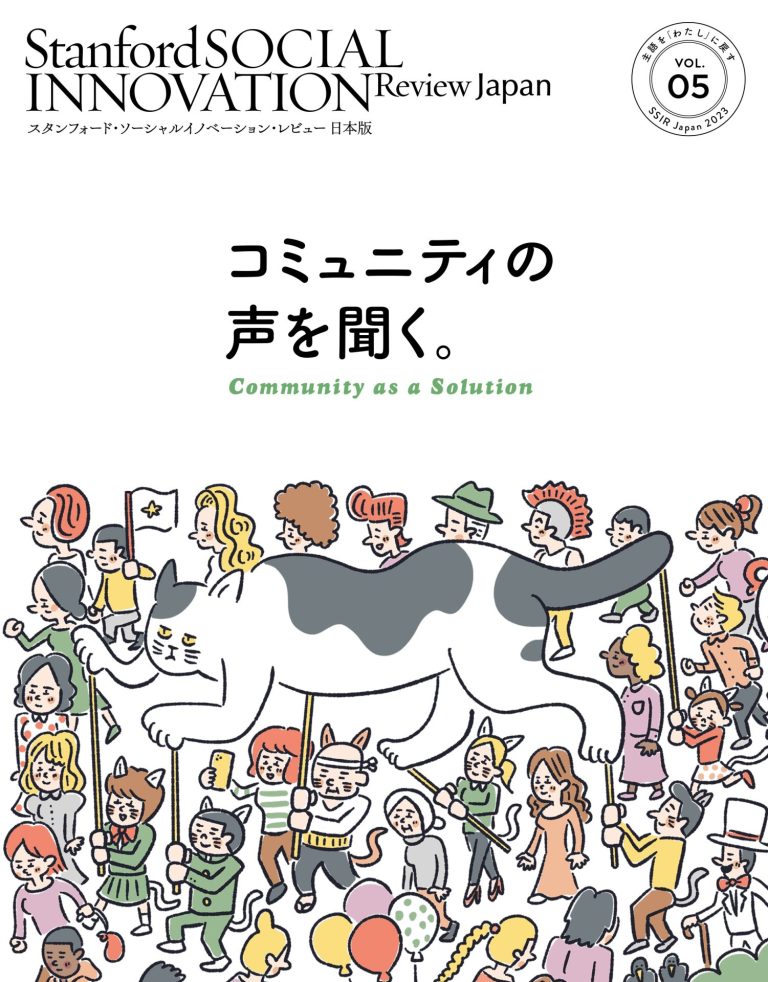日本企業が切り拓く価値共創型リサイクルビジネス: 生産者も消費者も「参加したくなる」循環のつくり方
リサイクルには落とし穴がある。
優れた技術があっても回収の仕組みがなければ価値がないし精巧な仕組みでも押しつけと受け取られれば消費者は参加しない。このジレンマをまったく新しい方法で乗り越えた日本環境設計(JEPLAN)とバリューブックスの取り組みを紹介する。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 02 社会を元気にする循環』より転載したものです。
荻野進介 Shinsuke Ogino
無駄にしない努力」から「価値を生む仕組み」へ
リサイクルといえば、身の回りの不用品を業者や自治体に無償、あるいは有償で引き取ってもらうこと、と考えてはいないだろうか。むしろ重要なのはその先、つまり回収されたものがどのような経路をたどり、どう処分されるのかを、消費者自身が意識することにこそあるが、そこまでの関心の高まりはいまだ感じられないのが実情だ。
そうしたなか、人々が進んでリサイクルに参加・協力する仕組みを構築している企業が現われている。多くの人をして不用品を持参させ、その行く末に関心を払わせ、次もまた持参しようと思わせる。そんなかたちで、商品あるいは物質の循環の輪を巧みに廻しているのである。
最初に紹介する企業は、神奈川県川崎市に本社がある日本環境設計(2022年6月1日付でJEPLANに社名変更)である。不要になった衣服やプラスチック製品を、消費者自ら、それらを購入した店舗に置かれた回収ボックスに持参する。それらを、各素材に応じてリユース・リサイクルするだけでなく、素材によっては自前の技術と協力会社の技術を用いて最初の原料にまで戻し、メーカーや商社に素材として売る(もしくは素材から製作した商品を消費者に売る)というユニークな事業を展開している。
もう1社は長野県上田市で古本ビジネスを展開するバリューブックスである。買い取り希望のユーザーが送ってきた古本は需給の関係などから、回収したうちの半数は値がつかず、廃棄、つまり紙レベルのリサイクルに回さざるを得ない。この貴重な本という商材が日々大量に廃棄されてしまう現実に向き合い、何とか別のリサイクルや活用法はないかと模索し、実行している日本最大級のネット古書店である。
本稿では、この2社の事例から、循環型経済をさらに拡大させるための企業のあり方を考えていきたい。具体的には、生産者も消費者も参加したくなる価値共創型リサイクルビジネスを企業が回していくためのポイントを、❶ハブを担うプレイヤーの存在、❷消費者起点で回す、❸回転することでブランド化し、自律的に回りつづけるようになる、という3点で整理し、「循環のジャイロ」としてモデル化していく。
ボトルからボトルへのリサイクル
長さ数ミリの直方体に近い、白いペレット(小さな塊)。神奈川県川崎市の臨海部に位置する日本環境設計の子会社・ペットリファインテクノロジーで製造されているそれは、ペットボトルの原料となる樹脂である。何からできているのかといえば、何と使用済みのペットボトルなのだ。同社は、使用済みペットボトルを分子レベルまで分解し、汚れや色、異物を取り除いたうえで、再びペットボトルの原料として使える材料にする技術(ケミカルリサイクル)を商用で実現する、世界で唯一の会社である。

1997年施行の容器包装リサイクル法により、日本ではペットボトルの約90%が自治体によって回収されているが、その多くは破砕、洗浄され、再生樹脂として生まれ変わり(=メカニカルリサイクル)、海外などに輸出される。それらはペットボトルや衣服などに生まれ変わるものの、3回以上のリサイクルは難しく、最終的には焼却されてしまう。もう一度、新品に生まれ変わる「ボトルからボトル」のリサイクルは、回収率が世界でも抜きん出て高い日本においても10%ほどしか行われていない。
同社の親会社にあたる日本環境設計会長の岩元美智彦が話す。「前事業会社からこの事業を買収したのが2018年3月で、プラントが稼働を始めたのが2021年10月です。補助金に頼ることなくプラントを稼働させ、本格的に商用での運用がなされていて、利益も出ています」。
ペットリファインテクノロジーでは京都市や釧路市など、いくつかの自治体と提携し、回収されたペットボトルの引き受け(購入)を決めた。「ペットボトルがペットボトルになる。こんなにわかりやすいリサイクルはありません。子どもたちにこの話をすると目を輝かせるんです。これが広まれば、ペットボトルをつくるために、石油を掘り出さなくて済む。これまで、衣服、プラスチック製品、携帯電話などのリサイクルに携わってきましたが、自治体と組んでやれるペットボトルは回収が効率的でインパクトが大きい。リサイクルの最優先課題として力を入れていきたい」。
服からバイオエタノールをつくる
岩元は大学を卒業後、大阪の繊維商社に入り、営業マンとして働き、回収したペットボトルからつくった再生ポリエステルの用途開発に携わっていた。2006年、たまたま読んだ新聞記事で、トウモロコシからバイオエタノールが生成可能だと知り、「トウモロコシと同じ植物である綿からも、バイオエタノールがつくれるのではないか」とひらめいた。
異業種交流会で知り合った大学院生、髙尾正樹に話すと意気投合、古着のTシャツを用いて技術開発に成功する。2007年に2人で創立したのが日本環境設計だ。「工業用の基礎原料となるエタノールは、プラスチックはじめ、さまざまな製品に転化させることができますし、車などの燃料にもなる。このリサイクルを広範に活用すれば、我々が生きていくのに欠かせない石油への依存度が大きく低下する。地下資源を必要としない社会が生まれるかもしれない」。
技術は手に入れた。次は“原料”となる古着をかき集めなければならない。が、企業や役所を回っても色よい返事は得られなかった。五里霧中のなか手を差し伸べてくれたのは、良品計画の金井正明社長(現会長)だった。「小売店やメーカーがものを売るだけの時代は終わった。これからは、使い終えたものを集めるところまでやって初めてお客さんがきてくれる」(岩元、2015)と声をかけてくれたのだ。

古着でデロリアンを動かす
その後、経済産業省管轄の繊維製品のリサイクル調査事業に応募したところ、採用された。その調査事業から生まれ、2010年にスタートしたのが、「FUKU-FUKUプロジェクト」だ。
消費者が要らなくなった衣服を、良品計画はじめ、小売店の店頭に置かれた回収ボックスで集める。段ボールでつくられた回収ボックスには、服を持ったハチが描かれている。いろいろな花から蜜を集めて糧にする習性から、いろいろな場所から服を集め資源をつくりだす仕組みをハチで表現した。「FUKUは服と福をかけています。服は地球の福になる資源だと。
リサイクルしましょうと呼びかけるだけでは、消費者は動きません。彼らの心を動かすにはリサイクルの社会的意義を強調したスローガンより、心に残るブランドが重要です。その象徴がFUFU-FUKUであり、ハチなのです」
岩元は、遊び心いっぱいの仕掛けも用意した。アメリカ発の大ヒット映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。岩元も大学時代に観て感動した。その劇中に、タイムトラベルができる自動車、デロリアンが登場し、開発者であるドクがゴミを燃料にそれを走らせるシーンがある。映画の中でのその日は、2015年10月21日⸺。

岩元は映画を製作したユニバーサル・スタジオ本社と交渉して公認を取り付けると、デロリアンを、回収した衣類でつくったバイオエタノールで走らせるイベントを実行する。日付はもちろん2015年10月21日だ。その後、デロリアンを伴って日本全国で古着回収イベントを実施し、啓発と回収を同時に展開していった。「古着を持参するとデロリアンと写真が撮れるとなると、人々が平気で1時間も並んで待ってくれた。ワクワクして待っている間に、大人も子どもも地球環境の大切さとリサイクルの意義に気づいたでしょう」。このように、岩元の施策にはいつも消費者がワクワクして参加できる仕掛けがなされているのだ。
循環に必要な6つの要素
このプロジェクトは2017年から名称がBRING(持参する)に代わった。「服からバイオエタノール」ではなく、「服から服」をつくるように、リサイクルの中身も進化した。その背景には日本環境設計が2015年に開発した新技術がある。化学繊維のポリエステルを
分子レベルまで分解し、不純物を除去したうえで、もう一度ポリエステルをつくるケミカルリサイクルに成功したのだ。品質は石油由来の新品ポリエステルとまったく変わらない。先のペットボトルのリサイクルと同じ図式だ。
この「服から服をつくる」BRINGの仕組みを、岩元は次の図のように整理した。ハチのマーク、すなわち日本環境設計を中心に、6つの要素がまるでコマのように廻りつづけるこの図を、「循環のジャイロ」と名付けてみよう。
まず「消費者」が起点となり、プロジェクトに参加する小売りやアパレルの店頭に置かれた回収ボックス(「回収拠点」)まで古着を持参する。参加企業はFUKU-FUKUのスタート時は5社だったが、BRINGとなったいまでは約150社を数える。
そうして集まった古着は日本環境設計の分別センターで分別され、そのうち、ポリエステル製品は北九州市にある同社の工場で再生ポリエステルに生まれ変わる。ここではケミカルリサイクルの「技術」が活用され、他の繊維が混紡しておらず、染色材などの不純物もない「素材」に生まれ変わる(ポリエステル以外の製品はパートナー企業でリサイクルされる)。
こうしてできあがった再生ポリエステルは、石油由来のものと同じ品質でありながら、新たな石油資源から精製されるわけではないため環境負荷が低い。しかも、従来の方法でつくられた再生ポリエステルと比較し、49%の二酸化炭素排出削減効果があるという1。
そのため、アパレルなどのメーカーや商社には、サステナブルという付加価値を得た素材として納めることができる。素材の商品名はBRINGMaterialである。商社はこれをメーカーに売り、メーカーはこれを使ってつくった服を、小売りする。そこからこのモデルが2巡目に入るというわけだ。
しかも日本環境設計はメーカーと小売りの機能も備える。再生ポリエステルを使い、その名もBRINGというブランド名で、アウトドアウェアを中心とした自社製品をつくっているのだ。2020年4月にネット通販を本格的に開始、2021年11月には実店舗を東京の恵比寿に開店した。
このように、6要素すべてに関わるハブとして日本環境設計が機能することで、「循環のジャイロ」が廻っている。

循環のジャイロモデルを動かす3つのポイント
では、この日本環境設計が構築した「循環のジャイロ」をモデル化することはできないだろうか。そのヒントも、岩元の言葉にあった。「リサイクルといえば、皆さんこう言うんです。この6つを回していくのがリサイクルだと。でもそう簡単には回らない。なぜかといえば、6つそれぞれが孤立しているからです。消費者の意識が低いからできない、回収拠点が少ないから無理だ、技術が未確立、素材のレベルが低い、素材を使うメーカーがない、小売りをしてくれない……それぞれが、自分以外の要素が原因だとするんです。真伨な対話をすれば解決するのでしょうが、それもない」。
解決するにはどうしたらいいのか。「真ん中に、誰かが必要なんです。消費者のこと、回収拠点のこと、技術のこと、すべてを理解し、すべてを調整する能力を持った、人と組織です。それをやってきたのが日本環境設計なんです」。
ここまでの話から、「循環のジャイロモデル」のポイントを導き出してみると、次の3点が見えてくる。
❶ ハブを担うプレイヤーの存在
❷ 消費者起点で回す
❸ 回転することでブランド化し、自律的に回りつづけるようになる
1点目は、ジャイロの中心で、関係する全プレイヤーにアプローチし、情報整理から協業までを促す存在の必要性だ。結果、これが責任を押しつけ合う関係性から協力し合う関係性への転換へとつながっている。
2点目は、あくまで消費者からスタートする、という「起点」の話だ。もし日本環境設計が、「素晴らしい技術をつくったから」と、それを各プレイヤーに持っていっても、決して見向きもされなかっただろう。デロリアンイベントなど、消費者が参加したいと思う仕組みを構築したからこそ、小売りもメーカーも動き出したのだ。3点目は、本稿後半で詳しく解説する。
消費者を起点に、マクドナルド本社も動かす
日本環境設計は衣服のほか、プラスチックの回収も手掛けており、FUKU-FUKUと同じく消費者と企業を巻き込んだ「PLA-PLUSプロジェクト」を2012年から運営している(現在の名称は「BRING PLAPLUSプロジェクト」)。
そのほか、企業と個別に実施している回収プロジェクトもある。代表格が、日本マクドナルドが2018年から行っている「おもちゃリサイクル」の支援だ。子どもが遊ばなくなった、ハッピーセット付属のプラスチック製おもちゃを店頭で回収し、店内で使用するトレーなどにリサイクルする。マクドナルドのアメリカ本社からもSDGs担当者がこの取り組みを学びに来たという。結果、2021年9月、マクドナルドは2025年末までに、ハッピーセットのおもちゃの素材には再生可能なものしか使わないようにすると宣言した。消費者が回収に楽しんで参加できるこの仕組みは、まさに❷の消費者起点の力を物語っている。
また、扱う素材を増やすことは、ジャイロに巻き込めるプレイヤーの数を増やすことにつながる。現在、同社の仕組みに参加している企業の数は、国内外合わせて300社を超えている。

小遣い稼ぎで古本をネット販売
日本環境設計のように、技術、回収の仕組み、ブランドなどを持ち合わせていなければ循環のジャイロは廻せないのか。そうではないことを示しているのが、古本の買い取りと販売を行うバリューブックスのケースだ。ごく普通のオンライン古書買取販売をしていた同社が循環を廻すプレイヤーへと進化する道筋から、このモデルの組み立て方が見えてくる。
同社は2005年、創業社長、中村大樹(現取締役)の軽い気持ちと行動からスタートした。中村は、大学を卒業しても普通に就職する気がなかった。起業も考えたがうまくいかず、懐はさびしくなる一方。いい小遣い稼ぎがないかと思ったら、Amazonがあった。
個人が身の回りのものをAmazonのマーケットプレイス(電子取引プラットフォーム)で売るのが流行っていたのだ。中村本人はこう話す。「大学時代の教科書や趣味で読んだ本を出品したらその日のうちに売れた。これはすごいと。それからブックオフで古本を買ってはAmazonで売ることを繰り返すようになったのです」。
狙ったのは専門書だ。「ブックオフは商圏が狭く、来店客層も幅広いとはいえません。結果、専門書が売れ残っていたんです。価格も安く、たとえば100円。それをAmazonで売ると500円になった。利幅が大きかった」。
そのうち友人も数名加わった。月に500万~600万円を売るほどの規模になり、2007年バリューブックスを設立、あわせて買い取りのためのサイトも開設した。専門書の買い取りに力を入れ、値付けも高くした。
創業当時のバリューブックスは、先のジャイロモデルでいうと「回収拠点」という1要素を担うプレイヤーにすぎない。仕入れ先は消費者ではなく別の古書店で、小売りもAmazonというプラットフォームを介してのことだった。6つの要素はバラバラで、当然循環も起こっていない。
「本の寄付」を事業に取り込む
当時は競合も少なく、売り上げは伸び、組織もどんどん大きくなった。だが、中村には違和感があった。「創業メンバーはともかく、新しく入ってきてくれた従業員たちが心配でした。従事してもらうのは仕入れた本を仕分けし、きれいにするという単純作業です。やり甲斐を感じられず、辞めてしまう人も結構いました。そこで考えたのです。人から感謝されるような仕組みをつくったらどうかと」。
それが2010年にスタートしたbook gift project(ブックギフトプロジェクト)である。ネット上の古書市場では供給過多で値段が極端に下がってしまい、売り物にならずに廃棄せざるを得ないベストセラーを、保育園や学童施設、老人ホーム、病院などに従業員が持参し、寄付する。「人から感謝されると従業員のモチベーションも上がります。買い取り顧客にも、買い取れなかった本はどうしたのかと聞かれたら、寄付というかたちで活用しましたといえる。せっかくつくられた本を捨ててしまう、という罪悪感もあった。従業員のやり甲斐不足、本を捨てる後ろめたさ、その2つが少し解消されました」。
この「本の寄付」はバリューブックスが主体となる取り組みだが、2012年から寄付を仲立ちするcharibon(チャリボン。チャリティ本の意)という仕組みもスタートさせた。NPOや大学、自治体といった社会性の強い組織への寄付を、バリューブックスへの古本送付というかたちで行う。バリューブックスは買い取った金額を、寄付者に代わって各組織の口座に古本送付者からの寄付として振り込む。NPOはそれで活動資金を賄い、バリューブックスは事業の根幹となる仕入れを確保できる。寄付者は要らなくなった本を寄贈することで、自らの寄付がかたちになる。3者がハッピーになる仕掛けだ。charibonは、大学が卒業生から寄付を集める際にも使われる。ジャイロモデルの「回収拠点」を増やす仕掛けといえるだろう。現在までに170のNPO、80の大学がこの仕組みを活用し、寄付の総額は累計で6億円を超えている。
2015年には本社のある長野県上田市に、カフェつきの古本屋NABO(ネイボ。デンマーク語で隣人の意)も立ち上げた。ネットに限っていた小売りをリアルにも拡大したのである(2021年より店名は「本と茶NABO」)。

寄付により消費者を巻き込み(結果としてより多く回収し)、自らが「小売り」機能を持つ。ジャイロモデルの上半分に留まっているが、バリューブックスにおける循環はこうして始まったのだ。
本が死なないエコシステム
2017年には、ジャイロモデルの下半分の領域にも足を踏み入れる。その打ち手の1つが、バリューブックス・エコシステムだ。
同社は値崩れして値段がつかず、廃棄せざるを得ない本であっても、先のbook gift projectなどを通じ、次の読者を見つける活動に取り組んできた。そうしているうちに、値崩れせず、次の読者が見つかりやすい本ばかりを刊行している出版社、すなわちメーカーの存在に気づいた。出版社別に買い取りデータを集計してみると、買い取り希望客から送られてきた本のうち、90%以上の高確率で買い取りが成立している出版社がいくつかあったのだ。「我々の考えに賛同してくれた4社がパートナーになってくれました。我々は彼らが出版した本を売って得た売上げの33%を彼らに還元しています。その使い道は、著者に還元したり、社会貢献のために使ったり、各社いろいろです。いい本を出す出版社が報われ、ますます多くのいい本が市場に流通する。本が死なずに生きつづける生態系(エコシステム)をつくりたいのです」。

2019年には「捨てたくない本」プロジェクトが始動。1日あたり同社に約2万冊送られてくる本のうち、廃棄、つまり古紙リサイクルに回さざるを得ない本は半分の1万冊にものぼる。それらのなかから状態のよいものを選び、単行本1冊50円、文庫本3冊100円といった格安の値段で販売する実店舗「バリューブックス・ラボ」を先のNABOの2軒隣にオープンさせた。
「本を捨てたくない」という思想に賛同する企業も現われた。日本環境設計の話でも出てきた良品計画だ。全国に約500店舗ある無印良品のうち、11店舗(2022年4月現在)で「古紙になるはずだった本」と題し、バリューブックスから仕入れた古本を販売している。

古本をノートに再生する
2021年、バリューブックスは、パートナーの力を借りながら、「技術」を用いて「素材」に戻し、「メーカー」として新しい製品をつくる活動にも挑戦した。
そのプロジェクトのリーダーをつとめたのが副社長の中村和義だ。「日本の古紙リサイクルのシステムはとても優秀で、製紙会社に届いた古紙のうち実に95%が新しい紙に生まれ変わるんです。その過程を製紙会社に行き、詳細に見学させてもらったうえで、こう考えたんです。それが本だったということを想起させる何かに生まれ変わったら面白いなと」。
その答えが、2021年1月に完成した「本だったノート」という名称のノートブックだ。本を再生紙に生まれ変わらせる製紙会社、その紙をノート用に印刷する印刷会社、ノートの体裁を決めるデザイナー、紙を束ね、紙ホチキスでとめる製本会社、というパートナー4者の力を借りてできたそれは、当初はノベルティ用に実験的に製作したものだったが、完成後の反響が大きく、一般向けにも限定販売された。「この反響を受け、市販品の開発を進めています。今後、先行発売を兼ねたクラウドファンディングも行います。今回は、文庫本を再生させてつくる文庫型ノートを予定しており、書店でも販売する予定です。本が別の形態で書店に戻るのです」。ところどころに、本だった頃の活字がまぎれこんだこのノートは、本が好きな消費者に抜群の訴求力を持つだけでなく、開く度に循環への意識を促すことだろう。

たゆまぬ改善で買い取り数もファンも増やす
バリューブックスも日本環境設計と同様、ユーザー、つまり本の消費者が自分たちの事業で要の存在であることをよく認識している。彼らが買い取りを希望し、不要となった本を送ってくれなければ、事業は成り立たないのだ。
同業のネット古書店と同社が違う点がある。不要となった本を送ってもらう際の送料だ。
買い取る側が負担することが多いが、バリューブックスは2018年から段ボール1箱につき500円を送料とし、買取査定額から差し引くように変更した。その代わり、買取金額をそれ以前より1.5倍にアップさせた。この点が他のサービスとの大きな違いである。
送料を一律で負担すると、買い取れない本の送料も全体の買取価格に影響してしまう。買い取れない本が多いほど、買い取れる本の買取価格が下がるからだ。中村大樹が話す。「何でも送ってください、送料無料です、というほうがユーザーの反応はいい。うちも含めて業界全体がそのやり方だったのですが、輸送費がかかり、段ボールがたくさん使われるため、環境面でも問題が大きいと思っていました。そこで、送料を有料にし、買い取れない本を処分するためのコストがかかっていることをユーザーに認識してもらうようにしたんです。その分、値段がつく本を、それまでよりも高い価格で買い取りますと」。
数冊だったら、売れそうな本、売れそうにない本を判断するのは簡単だが、大量の場合はどうしたらいいか。2019年、同社は「本棚スキャン」という仕組みを導入した。買い取り希望の本を、タイトルがわかるように横に並べて、スマホで写真を撮るだけで買取額がすぐにわかる仕組みだ。「これを使えば、買い取ってもらえる本だけを売ることができる。段ボールも運送費も節約できる。何より古本を段ボールに詰め、当社に送ったはいいが、これくらいの額にしかならない、買い叩かれたと、がっかりされるユーザーをなくしたい」。
最近は自社のECサイトも充実させている。在庫の有無は関係なく、あらゆる本をジャンル別、定価と比べて何%という価格別、書齢(出版日からの年月)別、人気別に検索することができ、買取参考価格まで出るのだ。「Amazonではここまでの検索は無理です。書齢が長いのに、値段が落ちておらず、人気が高い。これは良書だと。バリューブックスのサイトでは、そういう判断ができる。この機能を楽しみ、ここで買ってもらう本を増やすとともに、ファンも増やして、買い取りも拡大させたい」
技術の有無とブランド
ここまで、日本環境設計とバリューブックスの2社の事業を、先ほどのジャイロモデルを使って見てきた。
両社ともにジャイロモデルのハブとなり、消費者を起点にそのモデルを廻そうとしている点が共通している。両社の違いは技術だ。日本環境設計は自前で技術を開発しているが、バリューブックスは技術を持たない。紙のリサイクル技術がすでに確立しているからだ。それでも、その技術を持つ製紙会社と提携し、「本だったノート」という商品を開発している。
消費者をその気にさせるために、日本環境設計はリサイクルの「楽しさ」を訴える。デロリアンであり、ハチのマークである。FUKU-FUKU、BRING、PLAPLUSといったプロジェクト名も工夫されている。「ボトルからボトル」「服から服」というわかりやすいメッセー
ジを発信することも忘れない。一方のバリューブックスが訴えるのは「便利」と「公徳心」だろうか。前者の象徴は本棚スキャンであり、ECサイトの工夫、後者はbook gift projectであり、charibonだ。
日本環境設計のBRINGは素材から製品、回収までを通貫したブランドになっていることにも注目するべきだ。本稿前半で「❸回転することでブランド化し、自律的に回りつづけるようになる」としたが、BRINGのブランド価値は、ジャイロが自律的に廻りつづけることで高まっている。バリューブックスも今後はこうしたブランドをつくり上げる必要があるのではないだろうか。

ジャイロモデルを強化する打ち手
このジャイロモデルの輪をより大きく、より太くするにはどうしたらいいのか。両社はそのための試みにも乗り出した。
日本環境設計が取り組んでいるのが海外展開だ。2020年9月、エネルギー分野において世界最多規模のライセンスの数を保有するフランスの化学企業Axens(アクセンス)と提携した。岩元が話す。「同社はいわばプラント設計の大元を握る世界的企業です。既存のプラントを一部改良し、我々の技術を搭載した設備を加えると、ペットボトルやポリエステルなどが再生できるリサイクルプラントに変更させることができるんです。現在、同社は複数の国でアプローチを展開しており、ここ2年のうちに最初の結果が出るでしょう。リサイクルは日本だけではなく、世界規模の課題です。多くの戦争は石油や石炭といった地下資源の争奪戦から始まります。ケミカルリサイクルが世界に普及することで、“地上資源”で必要な分をまかなえるようになれば、これ以上地下資源を掘り出す必要はなくなります。(資源をめぐる)戦争を根絶するのも夢ではありません」。
一方のバリューブックスが取り組んでいるのが、業界を超えて同志を広げること。具体的には「Bコーポレーション(B CorpTM)」という企業認証制度の取得を急ぐ。B Corpは2006年にアメリカで設立されたB LabTMという非営利組織が認証する民間の認証制度で、株主だけでなくて環境や社会など、すべてのステークホルダーに配慮して事業活動を行うことを目指す。
同認証を取得した日本企業はまだ11社だが、世界では5000社以上にのぼる(2022年5月6日現在)。バリューブックスは取得に向け、自社のアセスメントを進めるとともに、B Corpの手引ともいえる『B Corpハンドブック』日本語版の翻訳出版にも取り組み、6月下旬の発売に向けて準備中だ。出版社という「メーカー」にもなるのだ。
同社でこのB Corpプロジェクトを担当する取締役の鳥居希が語る。「5つの領域(ワーカー、コミュニティ、エンバイロメント、ガバナンス、カスタマー)に関するアセスメント項目があり、それをひたすら改善していく必要があるんです。これを取得すると、私たちが取り組んできたような、従来の古本ビジネスの歪みを是正する取り組みが客観的指標に基づいて行えるようになる。B Corpが知られるようになれば、それを通してバリューブックスの認知度も上がるでしょうし、ハンドブックの発刊によって同志の企業が増える。『日本および世界中の人々が本を自由に読み、学び、楽しむ環境を整える』という私たちのミッションが実現しやすくなるのではないかと思っています」。
MOTTAINAIの限界を超えて
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したのがケニア人、ワンガリ・マータイである。2005年に来日した際、「もったいない」という日本語に感銘を受けたという。我々日本人がよく使うこの言葉は、他の言語に翻訳できない。マータイはこの美しい日本語を、地球環境を守るための共通語、「MOTTAINAI」として世界に広めることを提唱した。
だが、このMOTTAINAIだけでは、リサイクルの輪は廻り切らないのではないか。それは、物を無駄にするのは悪いことだ、という後ろ向きの感情に訴えているからだ。それに対し、楽しさやワクワク感、世のため人のため、便利といった前向きな感情、言ってみれば人間の心に訴えることが不可欠だということを、この2企業がつくりつつある価値共創型のモデルは教えてくれる。そのためには、循環の輪の真ん中に、ビジョンを示し、持続可能な活動を支えるリーダーや組織が不可欠なのだ。
(文中敬称略)
【写真】Sigmund on Unsplash
荻野進介 Shinsuke Ogino
1966年埼玉県生まれ。一橋大学法学部卒業。文筆家。主に人事、雇用、経営分野で執筆。
PR会社、リクルートワークス研究所などを経て独立。知識創造理論の創始者である経営学者、野中郁次郎・一橋大学名誉教授との共著に『史上最大の決断』(ダイヤモンド社)がある。
その他の著書に、『水を光に変えた男』(日本経済新聞出版)、『サバイバル副業術』(ソフトバンククリエイティブ)、『人事の成り立ち』(共著、白桃書房)がある。
注)
- デロイトトーマツコンサルティング「ケミカルリサイクルの二酸化炭素削減効果と脱炭素社会システムとしての評価検証委託業務成果報告書 令和元年度」2020をもとに、日本環境設計が自社使用電力のCO2排出量に換算して算出。
参考文献
『「捨てない未来」はこのビジネスから生まれる』岩元美智彦、ダイヤモンド社、2015年
「古本ビジネスの『おかしい』を変えたいバリューブックス」石井英男、ASCII、2021年、https://ascii.jp/elem/000/004/074/4074515/
取材協力|廣畑達也
写真提供(文中)|日本環境設計株式会社、篠原幸宏(バリューブックス)、株式会社良品計画